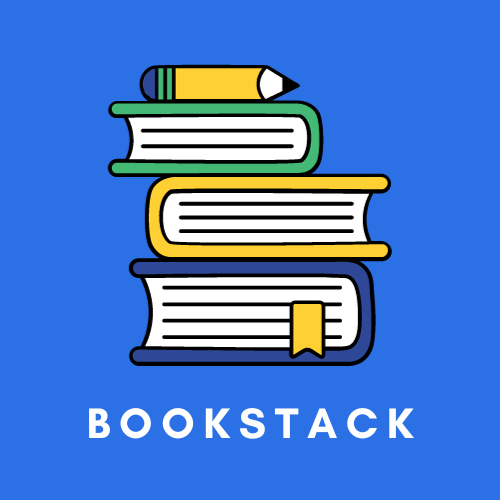ギガジン編集長の本
お盆休みということで過去にKindleでハイライトした文章を漁っていると、
GIGAZINE編集長の山崎恵人さんによる『GIGAZINE 未来への暴言 / 山崎恵人』の読書メモを発見した。
ブローガストの勢いを借りて、軽くブログとしてまとめてみようかなと。
個人的に印象に残った部分をつらつら書き残していきます。
(できるだけ今の時代に読んでも面白い部分を優先しました)
GIGAZINEは各カテゴリの記事がトップページに時系列順にずらっと並んでおり、一般のニュースサイトにあるような細かいカテゴリ分けというのをしていません。これは、専門バカになってはいけない、というメッセージです。
いわれてみれば、大きなカテゴリ分けしかないし、タグみたいなのは存在しない設計。
ネットの出現前から 専門バカ というのは登場していました。その極端なケースが音楽です。
冒頭からなかなか飛ばした物言いが好き。でも確かにそうなのかも。
「理性・知性・感性」のバランスについての話も面白かった。
・知識を脳内ではなくネット上などの外部に貯め込む
・どこかに貯め込まれている知識を効率よく引き出すための連想力と発想力
・必要な知識を教養として身につけるための仮想体験・仮想経験
ネットの場合はそうはいきません。どこが一番最初の情報源なのか、それは信じるに値するのか、本当のことなのか?常にそういう 真偽確認の戦い、ソースの確認の戦い です。
書籍だとちゃんと原典にあたりやすいですしね、インターネットはそこが難しい。
その中からYouTubeの運営陣がGoogleを選んだ理由、それが「法的に戦ってくれる弁護士軍団を所有していること」 でした。つまり、YouTubeは最初から「著作権」 という法律と正面から戦うことを前提とし、 著作権の概念を破壊することを目的としている企業だったわけです。
YoutubeとGoogleが組んだ経緯を詳しく知らなかったけれど、そうなんだ・・・。
ユーザーの忠誠度が高いにもかかわらず、その忠誠心を裏切って壊滅しかけているのが音楽業界です。
Bandcampや高額のアナログレコードがわりとメジャーになり、昔より少しはマシになったのかな・・・?
他にもファンがパトロンになる「パトロンモデル」成立への道についても詳しく書かれていて、「投げ銭が当たり前になる」という現代をこの段階から予想していたのはすごいなと
変化は不可避であり、その変化にいち早く適応したところが一番生き残る確率が高いわけです。
そのときにいかにして効率的に、手軽に、抵抗感無く金銭を移動させるか? その手法を確立させたところが今後の覇権を握る可能性が大きいですし、逆に言えばこのような少額決済をさらに下回る超少額決済をどこが提供するのか、それは一企業がすべきなのか、それとも資金移動専門の国際的機関を新たに設立すべきなのか?そういう問題が新たに発生するはずです。
少額決済システムというのは、現在の勝利者であるAmazonやAppleをも倒す可能性がある と言えば、かなりわかりやすいはずです。
少額決済を獲ったところが最強、みたいな話はほかのビジネス本でもよく読むけれど、
日本では意外とまだ流行ってないような。(Paypayが一番近いんだろうけれど)
中国だとその辺うまくやっている印象。
もっともっと各自が自分自身に関する情報で共有可能なものについては積極的にインターネットという場に提供して後続のために残していく、いわば ライフログとでも言うべき活動を積極的に展開できる下地作り、さらには現実の世界とネット上の情報とをつなげて連携させる仕組みの充実が必要 です。
ライフログ、という言葉はずいぶん前に聞かなくなってしまったけれど、
AIの時代だからこそLifelogブームはまた来る気はしているんだよね。
学校というのは現代社会において最初で最後の防波堤 なのだ、という意識が必要なのではないかと常々考えています。
AI時代における教育現場を考えると、これは今だからこそより響く話。
それでもなお、高校や大学が存在し続ける理由はとりもなおさず、「無理矢理にでも環境の力で勉強させる」 という点にありますし、まだまだインターネットだけで全てが完結できるわけではないためです。
小学校・中学校といったレベルの教育内容であれば暗記は必須ですが、それよりも先の専門分野になってくれば、必要なのは適切な情報と知識をインターネットから取り出す取捨選択の力になります。
暗記教育が無意味になったのは、AI時代以前のインターネット時代から。
今は適切な情報と知識をAIからどう取り出して活かすか、みたいなのが重要なんだろうなと。
ネットで検索して得た知識を実際に自分の生活や自分の身に起きている問題に当てはめて実行していくこと、それが究極の試験問題です。
うーん、確かに。
すなわち、 インターネットが存在する以上、今後は問題を出す側の能力も同時に問われる のだ、ということに他なりません。
これも人工知能の時代にも通用する話。
実際には各自の好みはバラバラであり、結局はニッチの集合体でしかないという実態を明らかにしました。こうなってくるとインターネットはかなり有利な場だということがわかります。というのも、 インターネットの利用者自体の傾向として、「自分の好きなものしか見ない」 ためです。
だからこそ、 GIGAZINEはカテゴリを細分化してニッチを狙うのではなく、あらゆるニッチを狙うという方針 で運営してきた、という次第です。
確かにインターネットから食レポまで、膨大な記事を出しているのに、どれもニッチどころを攻めている印象。
本当に 人間一人が知ることができる情報の種類はこんなにも増えているのに、知ろうとする情報の幅はどんどん狭くなるばかり です。
インターネットを利用する人が増えれば増えるほど、このもうひとつの世界は仮想世界ではなく、現実の世界の完全な鏡像世界、双子でうり二つの世界としての側面を強めていくはずです。
メタバースうんぬんはさておいても、インターネットは「現実の世界の完全な鏡像世界」という認識は大切。
また、面白い特徴として、 ポジティブなコメントを残す人はあらゆることについて大抵ポジティブな反応をしており、ネガティブなコメントを残す人はあらゆる事についてネガティブな反応をしている、という事実があります。
ということは、 真に問題となるのは、普段はポジティブな評価を下す人がネガティブな評価を下した場合、さらには普段ネガティブな評価を下す人がポジティブな評価を下している場合 です。
これも面白い話。実感としても首を縦に振るしかない。
10人中9人に嫌われてもいいから残りの1人に興味を持ってもらう」というのは、そういう小さな反応だけれども、大きな意味を持つ声を拾い上げるという作業の繰り返しであり、それは現実世界では音声情報として消えてしまうものを、インターネット特有の文字情報として記録される特性を利用することによって、要するに「検索」することで常に検証し続けることが可能になったからこそできる芸当、というわけです。
音楽や映画の一般人のつぶやきレベルの感想を検索できるのはインターネットのよいところ。
対価を用意していなくても、前借りする必要はない、自分に払える分だけを払えばいい、そういう可能性が残されているわけです。「パトロンモデル」 はそのギャップを埋める回答の一つです。
投げ銭の本質のそれ。
だからこそ、このパトロンモデルの実現は「教育」とセットでないと成立しない、と考えます。
確かに。
「インターネットの規則を考えるというのは世界の規則、世界のルールを考えるのと同じ」ということも言っていて、Open AIの動きを見てみるとまさにその通り、という感じ。
なんだか四方八方に散っているような感覚を抱くかもしれませんが、すべての方向性は「無料であるものに対価を払う」という方向性に向かうのだろう、ということです。
村上龍ぐらいアバンギャルドな世界観と物言いで、
この人がSF小説書いたら面白いだろうなぁ、とちょっとずれたことを思ったり。
糸井重里さんの『インターネット的』も含め、
「過去のインターネット未来予測」みたいな本はいくら読んでも面白いな~と。
長くなってきたのでそろそろこの辺で。
※8月に毎日ブログを書く試み「ブローガスト」10日目の記事です。